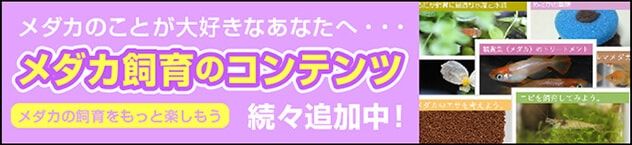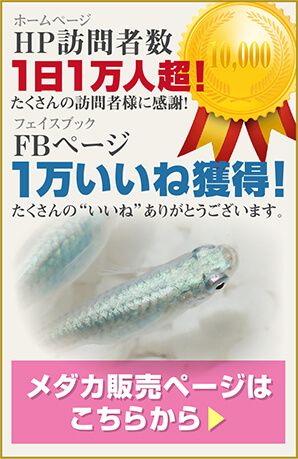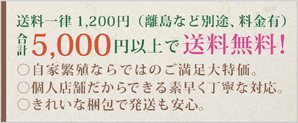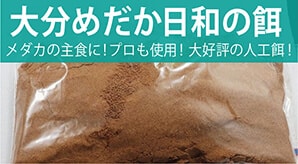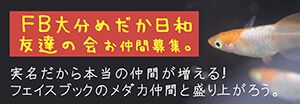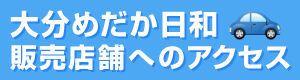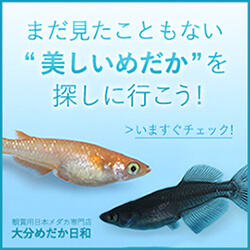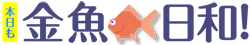スジエビってどんなエビ?メダカとの混泳はできるの?

メダカ水槽のパートナーといえば、まずはミナミヌマエビ、次にヤマトヌマエビなどが一般的だと思いますが、川や池にエビを採取にいった時、かなりの高確率で 紛れ込んでくるのがスジエビです。魚釣りの餌などにもよく使用されるスジエビですが、観賞目的で飼育する場合、メダカなどの魚類と混泳できるのでしょうか?

スジエビってどんなエビ?メダカとの混泳はできるの?のコンテンツ
1.スジエビの生態を知ろう!

スジエビとはテナガエビ科のエビのなの1種で、日本やその周辺の地域にも生息しています。細かく言うと、樺太、択捉島、国後島、北海道から九州、の島々、さらには
朝鮮半島の南部にまで生息しています。スジエビ属という分類にすると浅い海や汽水域にも生息していて、
淡水のスジエビと近縁の種ではイソスジエビとスジエビモドキの2種類がよくみられます。(私も小さなころよく海で見かけることがありました。)
今回紹介するスジエビとは淡水域に生息するスジエビのことで、魚釣りの餌や食用としても用いられることがある種で釣り餌として使用されることもあるために、
本来生息していなかったはずの沖縄等の地域にまで生息域を広げているという経緯もあるようです。地域によってはモエビ(藻蝦)やカワエビ(川蝦)といった
名前で親しまれていることもあります。
スジエビの特徴・餌、食性について

スジエビの外見の特徴としてはなんといってもその名前の由来になっているスジが入ったような黒褐色の帯模様でしょう。体に横方向の帯が入っているため、
大変わかりやすい特徴といえます。同じテナガエビ科ということもあり、テナガエビが小さいころはスジエビににています。他のヌマエビなどと違う特徴は
他にも腰の折れ方や、手足の長さ、ハサミの長さなどが違います。さすがに肉食性が強いということもありヌマエビと比べるとハサミは大きいようです。
スジエビの餌や食性については先ほどすこし触れましたがとても非常に肉食性の強い雑食です。藻類や水草も食べないこともないようですが、
ほぼ肉食性といっていいほどなので(よーく調べると結構、スジエビ藻類も食べるということでした)、観賞魚の水槽に入れてコケ掃除要員にしようという考えは
この時点ですでに意味が無い(混泳させる他の生体に注意すればコケ掃除要員にも使えないこともなさそうですが、相当慎重にならないといけない)ということがわかると思います。
野生のスジエビは何を食べているのかというと、主に水中に生息している水生昆虫や、小型の甲殻類、貝類、ミミズなどを捕食しています。もちろん、魚も補食する
ため、川魚の稚魚やメダカといった小魚をスジエビが補食することもあります。
さらには、動物の死骸に群がったり、餌が少ない状態の時は共食いすらおこないます。水中では亀や、ウナギやブルーギル、ブラックバスなど様々な肉食魚の
餌となっているようですが、アクアリストやメダカの飼育者に親しまれているミナミヌマエビやヤマトヌマエビと比べて、
かなりどう猛な性質をもつエビといえそうですね。
スジエビの飼い方

スジエビを飼育したいという方のために、強い肉食性という食性もあり、ミナミヌマエビやヤマトヌマエビほどは簡単ではありますが、飼育方法も紹介してみます。
まずは、入手方法ですが、釣り用の餌としても多く販売されており、簡単に入手できます。野生で採取しようと思った場合もミナミヌマエビや他のヌマエビ類と一緒に
よく混じっているので採取は極めて簡単です。(スジエビ混じっているのを気づかずにそのまま飼育していると他のヌマエビが
食べられてどんど減っていく場合もありますので気を付けてください)もちろん、魚釣りの餌にするほどなので大変、安価です。
水温は約28度程度までなら大丈夫ですが、比較的水温の低い環境を好むようで、水温の下がりがちな渓流等の低水温でも飼育できます。
日本の川魚が生活できるような環境なら問題なく飼育することができ、他のエビと同様、酸欠には弱いのでエアレーションはしておいたほうがよいでしょう。
餌に関しては、魚用の人工の固形飼料やエビ用の餌で普通に飼育できますが、なんといっても気をつけたいのが、餌不足です。
餌が足りてない場合、スジエビは簡単に共食いをおこします。稚エビ同士でも共食いはおこりますので餌には十分気をつけましょう。
比較的温和なミナミヌマエビなどと同じような感覚で大量にスジエビを投入してしまうと共食いがおこったり他の生き物に襲いかかったり大変なことになってしまいます。
さらに、活発で飛び出しがおこるため、蓋も必須です。基本的に夜行性のようですが、(他の生き物からすると寝ている時や活性が下がって動きが鈍くなっている
夜の方がスジエビが怖いですが)
昼間でも活発に活動してますので見ていて楽しむことができます。
▼日本在来のヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビだからこそ、安心してこんな綺麗なメダカと混泳できます
クリックして▶メダカの販売ページを見てみる

スジエビの繁殖・産卵について
スジエビの繁殖や産卵についてですが、繁殖期は春から秋までの間で、特に初夏には盛んに産卵します。繁殖方法は基本的にヤマトヌマエビに近いようですが、ミナミヌマエビのような環境でも繁殖できるようです。
簡単にどういったことか説明してみると、ヤマトヌマエビは卵から孵化してすぐの期間は、汽水域でゾエア幼生という形態となり、プランクトン生活をおくります。要は、産卵して
卵が無事に孵化し、ゾエア幼生とよばれるエビの赤ちゃんには汽水が必要ということです。
一方ミナミヌマエビ等の陸封型と呼ばれるヌマエビたちは、汽水域へ下ってゾエア幼生の姿でプランクトン生活を送るということはありませんので、
海と繋がっていない池であれ、水槽の中であれ、どこでも小さなエビの姿で孵化して稚エビが成長していきます。
そこでスジエビはというと、基本的にヤマトヌマエビと同じように汽水域でゾエア幼生となるようですが、生存率が極端に下がるもののミナミヌマエビのような
閉鎖された淡水でも繁殖することができるようです。汽水が必要なはずなのに淡水域でも繁殖できてしまうというのがすごい生命力ですね。
スジエビについて:まとめとメダカとの混泳
最後に、メダカとの混泳についてですが、いくつか紹介している動画のようにメダカとの混泳が可能か?不可能か?と言われると不可能ではないが、
メダカや他の生体を大事にしたい場合は混泳はさせないほうがいいと言えます。理由はもちろん、その食性によるものです。
実際は元気なメダカなどが襲われることが少ないとも言われますが、餌が足りない場合や、メダカが弱っている場合はあっという間に食べられてしまうようです。
もちろん、稚魚などはスジエビの恰好の餌になってしまいます。
他のヌマエビなども襲って食べるので一緒に飼育していると最終的に他のエビが駆逐されスジエビだけが生き残るということもよくあります。
どうしても、メダカや他のエビ、魚類と混泳させたい場合は最低限、スジエビを空腹状態、飢餓状態にさせないこと、スジエビを過密になるほど投入しないこと、
という条件を守ってください。もちろん、それでも弱ったメダカや生態は食べられてしまうのは避けられないので弱った生体はスジエビに食べられると割り切るしかないでしょう。
そこまでして、混泳させる意味はないような気はしますが紹介した動画のように実際に混泳させている方もたくさんいますので、
それは好みの問題ですね。メダカ屋さんとしては全くおすすめはできませんが・・・どうせ、混泳させるなら下記のようなヤマトヌマエビか
ミナミヌマエビがおすすめですよ(^^♪
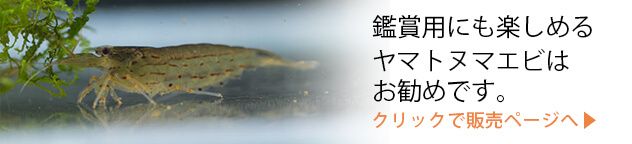
| Lサイズ 10匹セット 3cm前後 |