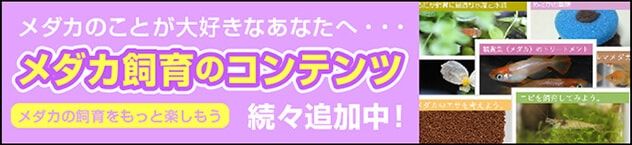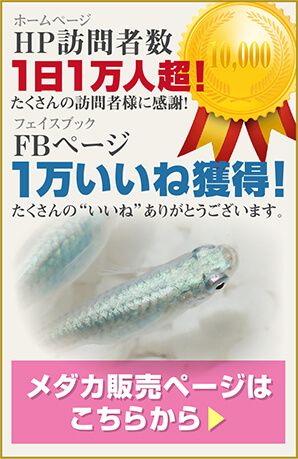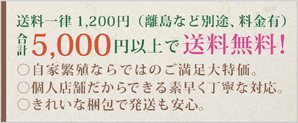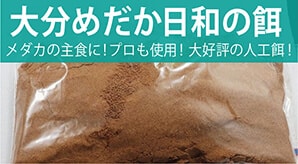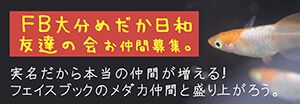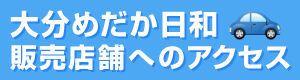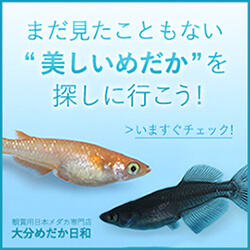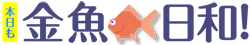ミナミヌマエビの繁殖・産卵の方法|初心者も簡単にできる繁殖の手順

ミナミヌマエビはメダカの飼育に限らず、ヤマトヌマエビと並ぶ観賞魚水槽の大定番ですよね。なんといっても人気の秘密は その飼いやすさ、繁殖のしやすさなどが気軽に楽しめるからではないでしょうか。それでは可愛いミナミヌマエビの繁殖方法について説明していきます(^^)これを 読めばきっと産卵~繁殖に成功できますよ。
| Lサイズ 10匹セット 2cm前後 |

ミナミヌマエビの繁殖・産卵の方法のコンテンツ
- ミナミヌマエビの繁殖と一生
- ミナミヌマエビを産卵させよう
- オスとメスはいますか?
- ミナミヌマエビの繁殖の季節・繁殖の水温は?
- ミナミヌマエビの交配
- ミナミヌマエビの抱卵の期間・孵化について
- 稚エビの誕生・ミナミヌマエビの幼生?
- ミナミヌマエビの繁殖を狙った環境作り
- ミナミヌマエビの繁殖までの過程で必要な道具
- ミナミヌマエビが抱卵しない・繁殖しない理由は?
- ミナミヌマエビの赤ちゃんの大きさ
- ミナミヌマエビの卵の色は黒い?緑?黄色?
- ミナミヌマエビは近縁種と交雑・繁殖する!
- ミナミヌマエビはボトルアクアリウム 水槽で繁殖 可能?
- まとめ
1.ミナミヌマエビの繁殖と一生

ミナミヌマエビの繁殖を狙うならまずはその一生を知っておきましょう。当店でも販売しているミナミヌマエビは日本や朝鮮半島、中国等に生息する
体調わずか3~4センチのヌマエビ(陸封型ヌマエビ)で流れの緩やかな川や池などの
水草が繁茂するような場所で生活しています。その寿命は野生では約1年と言われています。(人工飼育なら1~2年でしょうか)
なんでも食べるような雑食性ですがおとなしい性格なのでメダカとの混泳はもちろん、その環境下での繁殖も可能です。ヤマトヌマエビほどの
大きさもない為、水草の食害も生体への食害もほとんど心配のない愛すべきヌマエビです。その姿は原産地や生息地により個体差があり
基本は暗い青系ですが緑系だったり、赤系だったり、白系だったり色々です。
さてミナミヌマエビの一生のサイクルですが春~夏に産まれ、越冬し、次の春~夏に交配・産卵し稚エビを産み秋にかけて一生を
終えていくというライフサイクルで一生を過ごします。
こういった流れは(メダカの場合もそうですが)自然のサイクルであり、ヒーターなどを使って保温し、餌を与えるといった環境では
もちろん違ってくれるので気をつけてください。ミナミヌマエビは短命なので成体を購入した場合を思いのほか早く死んでしまう
ことがあるかも知れません。ただ、こういった場合は飼育していたミナミヌマエビの寿命だっただけで飼育環境には問題なかったのかも知れません。
短命であるがゆえ、閉じられた飼育環境での生態系で命を繋ぐには定期的にミナミヌマエビの繁殖を成功させる必要があるのです。
ですが、そんなに難しいものではないので安心してください(^^)ミナミヌマエビの飼育方法などはこちらも参考にしてください▶ヤマト・ミナミヌマエビの飼育方法。メダカ水槽の掃除屋さん
2.ミナミヌマエビを産卵・抱卵させよう

それではミナミヌマエビの繁殖について説明していきます。まずは産卵からですが、抱卵させようとタイトルにありますが、 ミナミヌマエビの場合、適温で飼育していれば勝手に抱卵してくれるはずです。(詳しくは後半で)ミナミヌマエビの卵は 黒い粒で抱卵した場合は(卵の色は時間の経過で黄色みを帯びてきたり、茶色っぽくなったりと色が変わってきます)お腹の下で黒い粒の卵をたくさんつけて、お腹の下で動かしているので観察していれば すぐに確認できるはずです。(後述しますがよーくみると抱卵・産卵の前にも背中の卵巣に卵が入っていれば存在が目視できます)とても簡単ですよね(^^)
3.ミナミヌマエビのオスとメスはいますか?オスとメスの見分け方

ペアや数匹で飼育しているんだけど全然抱卵しない!というあなた・・・ちゃんとオス・メスは入っていますか?
ミナミヌマエビの体は小さいのでわかりにくいのですが、ミナミヌマエビの尻尾の裏のひだが長い方がメスで、短いと方がオスです。
それと個体差もあるとは思いますが一般的にはオス(約2cm程度)よりもメス(約3cm程度)のほうがサイズが大きいとされています。じっくり観察してみてくださいね。
せっかく繁殖できる状態のミナミヌマエビが入っていてもオスとメスが入っていないことには何も始まりません。
追記:もう少しだけ詳しく、オスとメスの見分け方について紹介してみます。ミナミヌマエとオスとメスの違いですが、例えば腹部の形状でもわかります。
ミナミヌマエビのオスは腹部が直線的、メスはふっくらと丸みを帯びています。また、背腸の上を覆うようにうっすらと見えているのが卵巣で、コレは当然メスだけに見られます。抱卵が近づいているメスは
よーくみると卵巣の中に卵の形が見えています。この状態のメスとオスがいれば狙って繁殖させることも可能でしょう。
また、オスのミナミヌマエビはメスの匂いを嗅ぎ分けるために触角が発達している為、第一触角と呼ばれる触角がメスの1.5倍ほどに発達し伸長しています。これらの特徴をふまえて
個体を数匹比べてみるとミナミヌマエビのオスとメスを見分けやすくなるのではないでしょうか。
4.ミナミヌマエビの繁殖の季節・繁殖の水温は?

自然でのミナミヌマエビの繁殖のシーズンは8月や5月6月など色々な情報がありますが、要はミナミヌマエビが繁殖するのは水温が20℃前後で安定するような
季節(春から秋)ということのようです。地域や生息環境により変わってくるということですね。したがって人工的な繁殖を狙う場合は水温をヒーターを使い
この20℃前後に安定させるようにしましょう。屋内での飼育の場合は室温が安定しやすい為、放っておいても勝手に産卵しやすいです。
逆に真夏などは置き場所によっては水温上昇に耐え切れず死んでしまう場合もあります。
具体的には、ミナミヌマエビの繁殖に最適な水温は20~24度とされていて、この水温範囲内であれば、ミナミヌマエビは自然と繁殖行動を取りやすくなります。
ただし、ミナミヌマエビは水質の変化に敏感な生き物なので、ストレスを感じると脱皮してしまうことがあり、もし
抱卵中に脱皮してしまうと卵ごと切り離してしまうのでそうなると稚エビ・卵は死んでしまいます。抱卵中の水温の調整などに限らず、水換えなども慎重にしましょう。
5.ミナミヌマエビの交配と交尾
成熟したミナミヌマエビはメスの背中に白い筋模様が入り、産卵する状態に変わる為、脱皮します。その際、脱皮したメスのエビからは
フェロモンがでると言われオスはそのフェロモンに誘われてよってきて交尾をします。(交尾を終えたメスはフェロモンは出さなくなるようです。)
産卵が始まると2時間から3時間の時間を使い1つ1つ(約38-130個ほど)を抱卵していきます。エビの卵はお母さんエビがお腹に抱え孵化するまで
ずっとお腹にあります。よく観察しているとお母さんエビがお腹に抱卵している卵に新鮮な水を送っている姿がわかります。
卵は孵化するまでお母さんエビのお腹の中で成長を続けることになります。色々なところでみかける情報ですが抱卵には
月の満ち欠けが関係していると言われています。
6.ミナミヌマエビの抱卵の期間・孵化について
抱卵したお母さんエビのお腹の卵の中で順調に成長している稚エビは順調に成長していくと卵の色が透明になってきて 卵の中のミナミヌマエビの幼生の目がみえるようになってきます。孵化が近づいてきましたね。 抱卵してから、孵化するまでの期間は約2週間から4週間と言われています。 その間に抱卵していた卵を落とす場合がありますがその時は有精卵ではなかったか、水質の急変によりお母さんエビが脱皮をしてしまった ということが考えられます。そのタイミングでの水換えは特に気を使うようにしましょう。 メダカの時もそうでしたが水温が低めの場合よりも高めの時の方が産まれてくるまでの期間が短くなり早く産まれてきます。
7.稚エビの誕生・ミナミヌマエビの幼生?
ヤマトヌマエビなどと違い、
稚エビは海水を必要とせず淡水だけで成長できる為、いつの間にかお母さんエビのお腹から卵がなくなり、それから1日から2日後には水槽の中で泳いでいる姿を確認できます。
また、ヤマトヌマエビなどと違い、ミナミヌマエビはゾエアと呼ばれる幼生の期間はなく、卵から孵化した時点で親エビと同じ姿をしてみます。
孵化したばかりの稚エビはなかなか見つけづらいですが数はそれなりに孵化しているはずなのでよく見るとウィローモスや細かい水草の陰など色々なところに
いるはずです。産まれてからは水中のプランクトンや水槽や水草に生えたコケ、メダカの餌の残り、生物の死骸、デトリタスなど何でも食べて勝手に成長してくれます。
ここまでの流れでほとんど稚エビに関してのお話は終わりなのですが問題はここからです。せっかく誕生した、ミナミヌマエビの
稚エビもメダカや金魚など、観賞魚と一緒の場合はよほど隠れるところが多かったり、魚にたいしてエビの数が多かったりしないかぎりは
ほとんど大きくなる前にメダカや観賞魚に食べられてしまうことになります。(もちろん活き餌としては最高ですが)ミナミヌマエビを
本気で増やしたい場合はまず、魚類がいる環境で孵化させないことです。産まれた瞬間から恰好の活き餌となってしまいます。
なお、産卵を1回~数回繰り返したお母さんエビもそこで生命を終えてしまいます
8.ミナミヌマエビの繁殖を狙った環境作り

やっとここからが本題になるのですが、これが確実にミナミヌマエビを繁殖させる為の手順とルールです。
- ミナミヌマエビはメダカなどの魚類とは混泳しない
(稚エビを食べさせない為) - ウィローモスやアナカリスなどで水草の茂みをたくさんつくる
(稚エビの隠れ家となり自力で生き残れる環境をつくる) - 成熟したミナミヌマエビを20匹以上入れ、適度に光をあてコケがなくならないようにする
(コケが全く無いような環境なら毎日ごく少量の餌を与える) - ある程度成長するまではろ過フィルターなども必要なし
(稚エビが吸い込まれてしまう可能性が高い)使用する場合は網目の小さい スポンジフィルターを使用する - 季節を問わず繁殖させたい場合は水温を一定に設定
(ミナミヌマエビの繁殖に最適な水温の約20℃~24℃に設定) - 春先に購入した若いミナミヌマエビならたっぷり繁殖ができる
(屋内産まれの個体ならこの限りではありませんが)
ミナミヌマエビの繁殖までの過程で必要な道具
屋内での繁殖と屋外での繁殖で別々に書いて置きます。まずは屋内での繁殖を狙う場合から
- なるべく大きな飼育容器
(小さいほど水質の悪化が早くなるため) - 底床:大磯やソイル等
(バクテリアや底床の成分により水質を安定させるため) - 水草:ウィローモスやアナカリス
(水質の安定とエビの隠れ家のための丈夫な水草) - フィルター:稚エビが吸い込まれないような
(水質の安定) - エアポンプ
(酸素の提供に水の循環) - 照明:日光や室内灯だけではたりない場合
(稚エビの成長とコケの発生)
楽天市場をご利用ならお得に買い物ができる!
屋外での繁殖を狙う場合
- 発泡スチロール:保温性の確保
(適度に浅くて大きい方がよい) - 底床:大磯やソイル等
(バクテリアや底床の成分により水質を安定させるため) - 水草:ウィローモスやアナカリス
(水質の安定とエビの隠れ家のための丈夫な水草) - 必要な場合はエアポンプ
(酸素の提供に水の循環)
▼稚エビとは混泳できませんが、ミナミヌマエビがいっぱい繁殖できたら是非、混泳してみてくださいね(^^♪
クリックして▶メダカの販売ページを見てみる



10.ミナミヌマエビが抱卵しない・繁殖しない理由は?
それでは逆にミナミヌマエビが抱卵・繁殖しない理由を考えてみることにしましょう。もちろん、ミナミヌマエビが繁殖する条件の逆ということになりますね。
例えば抱卵しない理由は、水温が低い、餌が十分に足りていない、オスまたはメスがいない、飼育容器の中にミナミヌマエビの数が少ない(60センチ水槽に2~3匹しかいないとか)
ミナミヌマエビの個体が老個体であることなどが考えられます。
ミナミヌマエビは、水量の小さなボトルアクアリウムでも繁殖する場合があるほど、繁殖が優しい種類のエビです。
抱卵はしているのになぜか繁殖はしないという場合の原因で考えられるのは、脱皮をしてしまい卵がとれてしまっている、稚エビは生まれているのに即、魚に食べられてしまっている、
ありがちなのは、濾過フィルターの吸水口から吸い込まれてしまっているなどです。
どちらかと言えばミナミヌマエビを繁殖させることができない理由は、抱卵させることより、親エビから稚エビが離れた後、その稚エビが成長する環境が整っていない場合のほうが
多いのではないでしょうか。どれも解決策は簡単だと思いますのでどれかに思い当たらないか考えてみてくださいね。
11.ミナミヌマエビの赤ちゃんの大きさ
ミナミヌマエビはヤマトヌマエビなどがゾエアと呼ばれるよく知るエビの姿とは違う幼生から成長していくのに対し、ミナミヌマエビの赤ちゃんは卵から生まれるとすでにミナミヌマエビの親と同じ姿をしています。 ただし、ミナミヌマエビの赤ちゃんの大きさは0.1ミリ~またはそれ以下程度と、大きな種類のミジンコよりも小さいんじゃないかというぐらい小さいです。その為、メダカの少し大きな稚魚にすら捕食されるような大きさです。そういったこともあって 生まれて、他の生体に食べられたり、フィルターに吸い込まれたりしても気づけ無いことが多いのではないでしょうか。いなくなったミナミヌマエビの赤ちゃんがフィルターの中で成長していたなんていうこともよくある話しです。
12.ミナミヌマエビの卵の色は黒い?緑?黄色?
ミナミヌマエビの卵の色は何色?と質問されると難しい場合があります。それは、ミナミヌマエビの卵は黒かったり、緑色だったり、黄色(褐色?)だったりする為です。実際に詳しい原因はわかりませんが、
卵の色が黒でも、緑色でも黄色でもおかしいわけではなく、水質や餌、温度など環境、卵の成長の過程により変わってくるともされています。
単純にミナミヌマエビの卵の成長過程で、抱卵初期なら卵の中に何も見えず黄色っぽく見えたり、後期なら卵の中の稚エビが透けて見えて黒く見えることだってあるでしょう。いずれにせよ、抱卵しているのであれば
あまり卵の色まで気にすることはなさそうです。
ミナミヌマエビとごく近縁のレッドチェリーシュリンプやルリーシュリンプの卵は黄色だったりしますし、飼育しているミナミヌマエビが純血種なのか、近縁の種と交配しているのか、ミナミヌマエビと
違いがわからないくらい近い近縁の種なのか、そういった個体差でも卵の色が変わるということはあるでしょう。抱卵しているミナミヌマエビの卵を見て、透明になってきたからダメだとか、黒いから、黄色いから
ダメだといったような判断はできないということですね。(さすがに、体から離れて白くなったらカビが生えてるのでしょうけど)
13.ミナミヌマエビは近縁種と交雑・繁殖する!
ミナミヌマエビに限りませんがメダカにしろ、エビにしろ、地域により個体差があります。そしてミナミヌマエビは近縁のヌマエビとも交雑・繁殖します。例えば、レッドチェリーシュリンプなどの改良品種の
シュリンプとも簡単に交配・交雑してしまいます。それは、レッドチェリーシュリンプなどの改良元の原種がミナミヌマエビに近いヌマエビということで、交雑するのですが、もちろん他の海外産のヌマエビとも交配・交雑して
繁殖します。
その為、自然界では人間が外国より、釣り餌などにするために持ち込んだヌマエビと交配して実は現在では純粋なミナミヌマエビというものは希少な存在となっています。実際にペットショップで販売されているものも
ミナミヌマエビではない近縁種ということが多々ありますし、当店のミナミヌマエビも他の遺伝子が全く入っていないともいいきれません。
メダカにしろカラーシュリンプにしろ、人間が観賞用に改良品種した品種とも簡単に交配するのですから、それを自然界に放すことがどれだけ危険なことかおわかりになると思います。仮にミナミヌマエビを
飼育していて絶対に純血のミナミヌマエビだと確信があったとしても個体差などあるので絶対に飼育している個体を自然の河川に放流するということはしないようにしてください。
14.ミナミヌマエビはボトルアクアリウム 水槽で繁殖 可能?
ミナミヌマエビなどの小さなエビをボトルアクアリウムで飼育している人もたくさんいると思います。その中で小さなボトルの中でミナミヌマエビが繁殖したという方もいるはずです。私もボトルアクアリウムをやっていますので
ミナミヌマエビが住人のボトルもあります。はっきりいって水草を敷き詰めて繁茂させ照明をあててるだけのボトルの中でも条件次第ではミナミヌマエビの繁殖はできます。
簡単な条件はこの記事で書いたような条件で一定の水温を日照時間を満たした環境がある程度続けばいいのですが、そこまで気にしていなくてもミナミヌマエビをほぼ放置で飼育できる環境ができていれば飼育していくなかで勝手に条件が整ったタイミングで抱卵・繁殖しています。
小さなボトルの中で産まれる新しい命はとても嬉しいものですね(^^)ボトルアクアリウムについては、こちらの記事をご覧ください⇒ボトルアクアリウムの作り方!失敗しない為の大事な知識を身につけよう
15.ミナミヌマエビの繁殖のまとめ
いかがでしたか?もちろん、今回記載した飼育・繁殖方法が絶対ではありませんが、万全に万全を期した書き方をしました。
状況・環境により変わってくることもあると思います。
実際は、屋外でミナミヌマエビを出来上がった飼育水と一緒に発泡スチロールに入れてを放置しているだけで
勝手に繁殖して成長していることもあるぐらいなのでとても産卵・繁殖は簡単なんです。
なお、上の写真のようなチェリーシュリンプやルリーシュリンプなどの種類も
同様の方法で繁殖することができます。
エビの繁殖に挑戦したい方にはミナミヌマエビほど、安価でお手軽なものは無いと思います。ぜひチャレンジしてみませんか?
よろしければこちらからご購入してくださったら嬉しいです(笑)▶ ミナミヌマエビの販売